親鸞聖人が生涯の心の支えとされた、善導大師の物語「二河白道のたとえ」。
シリーズ第7回となる今回は、ついに物語の核心部分、「絶望の中でいかにして道を歩み出すか」という、魂の決断のシーンに入ります。
自分の力ではどうにもならない「死」の恐怖に直面した時、旅人が出した答えとは何だったのでしょうか。
言葉にできないほどの恐怖
火の河と水の河に挟まれた、わずか数寸(十数センチ)の白い道。
旅人はその前に立ち尽くしました。
「時に当たりて惶怖(こうふ)すること、また言うべからず」
(その時の旅人の恐れおののく様は、とても言葉では言い表せないほどであった)
前には荒れ狂う二つの河、後ろからは殺気立った群賊や猛獣が迫っています。
まさに絶体絶命。心臓が早鐘を打ち、足がすくむ極限状態です。
「三つの死」の自覚
パニックになりそうな中で、旅人は必死に状況を分析し、自分自身にこう問いかけます(自ら思念すらく)。
「我(われ)今 回(かえ)らばまた死せん、住(とど)まらばまた死せん、去(ゆ)かばまた死せん」
(自分は今、戻っても死、留まっても死、進んでも死しかない)
旅人は気づいてしまったのです。自分には「3つの死」しかないことに。
- 戻れば死ぬ: 後ろへ引き返せば、群賊や悪獣(煩悩や悪しき仲間)に殺される。
- 留まれば死ぬ: ここで立ち止まっていても、追いつかれて殺される。
- 進めば死ぬ: 前の細い道を進んでも、火や水に落ちて死ぬかもしれない。
どこへ行こうと、自分の力(自力)で助かる見込みはゼロ。
これは、私たち人間が、どんなに足掻いても「老い・病・死」という苦しみからは決して逃れられない事実(諸行無常)を突きつけられた姿そのものです。
「どうせ死ぬのなら」という大転換
「一種として死を勉(まぬが)れざれば」――どうあがいても死ぬ運命が変わらないのならば。
ここで旅人の心に、ある種の「開き直り」にも似た、強烈な覚悟が生まれます。
「我寧(むし)ろこの道を尋ねて前に向こうて去(ゆ)かん。すでにこの道あり。必ず度(わた)すべし」
(どうせ死ぬ身であるならば、私はむしろ、この白い道をたどって前へ進もう。現にここに道があるではないか。この道がある以上、必ず渡れるはずだ!)
「白道を歩む人」の誕生
戻る道も、留まる場所もない。
ならば、目の前に続いている「この道」に賭けるしかない。
この瞬間、旅人の心から「自分の力でなんとかしよう」という迷いが消えました。
「道がある(仏様の救いがある)」という事実だけを頼りに、一歩を踏み出す決意をしたのです。
自身の無力さを悟り、「自身の力では救われない」と認めた時、初めて「仏の道(白道)」を歩む本当の求道者が誕生する。
この切迫した決断の場面こそが、信仰の原点であると善導大師は教えているのです。
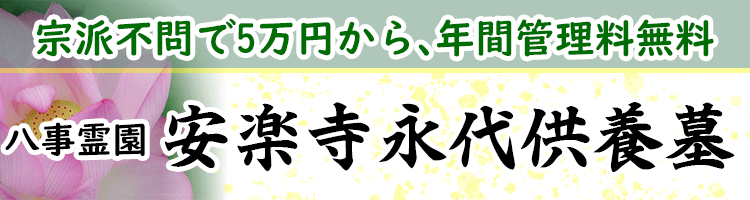



コメント