親鸞聖人の90年のご生涯をたどるシリーズ第5回。
今回は、承元(じょうげん)の法難により、流罪人として送られた極寒の地・越後(現在の新潟県)での生活と、そこで確立された「非僧非俗(ひそうひぞく)」という独自の生き方についてまとめました。
【親鸞聖人のご生涯⑤】流罪地・越後での生活。「非僧非俗」として民衆と共に生きる
承元元年(1207年)、親鸞聖人35歳の時。
理不尽な念仏弾圧(承元の法難)に対する行き場のない怒りを胸に、聖人は流罪の地・越後(えちご)へと旅立たれました。
1. 荒涼とした大地で見た「人間の真実」
都から遠く離れた越後の国府(現在の新潟県上越市付近)。
そこで聖人が出会ったのは、日本海の荒波と吹き荒れる雪風という「荒涼とした厳しい自然」でした。
そして何より、その過酷な環境の中で、その日一日を生きるのに精一杯な、貧しくもたくましい人々の姿でした。
それまでエリート僧侶として生きてきた聖人にとって、彼らの姿はどう映ったのでしょうか。
流罪人としての生活を通して、聖人は貴族や庶民、男や女といった区別を超えた、「飾らない、ありのままの人間の生き方」に深く目覚めていかれたのです。
2. 「肉食妻帯」という決断
この越後の地で、聖人の人生を決定づける大きな出来事がありました。
それは、妻・恵信尼(えしんに)様との結婚、そして子どもを授かったことです。
当時の僧侶にとって、肉を食べること(肉食)や結婚すること(妻帯)は、戒律で固く禁じられていました。
しかし聖人は、あえて「肉食妻帯(にくじきさいたい)」の道を選ばれました。 これは堕落ではありません。戒律を守れる「特別な人」として生きるのではなく、煩悩を抱えたまま、悩み苦しむ民衆と同じ「一人の生活者」として、お念仏の道を歩む決意の表れでした。
3. 「愚禿(ぐとく)」と名乗る
聖人は、自らの立場をこう表現されました。
「非僧非俗(ひそうひぞく)」
(僧侶にあらず、俗人にあらず)
髪を剃って僧侶の姿はしているけれど、心は煩悩にまみれた凡夫(ぼんぷ:平凡な男)である。しかし、ただの俗人でもなく、仏道を歩む者である。
そして、自らを「愚禿釈親鸞(ぐとくしゃくしんらん)」と名乗られました。「愚かな坊主」という意味です。
4. 愚かなまま、救われる道
煩悩を断ち切ることもできず、欲や怒りに振り回される愚かな私。
聖人は、そんな自分をごまかしたり、聖人君子のように振る舞ったりはしませんでした。
「人間としての愚かさ(煩悩)を抱えたまま、民衆のひとりとして生きる」
越後での日々は、自分の弱さを直視し、「こんな愚かな私だからこそ、阿弥陀様は救わずにはおれないのだ」という確信を深めていく、かけがえのない時間となったのです。
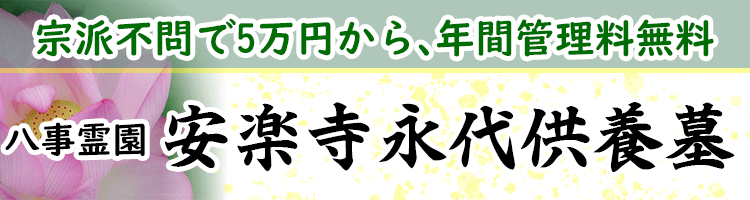



コメント