親鸞聖人が大切にされた善導大師の物語、「二河白道のたとえ」。
シリーズ第5回となる今回は、旅人がいよいよ「二つの河」の現実に直面し、立ち尽くす場面です。
ただ逃げてきただけでは済まされない。
「生きる意義を尋ねる心(求道心:ぐどうしん)」が試される瞬間の物語をまとめました。
絶体絶命! 目前に広がる「死の光景」
背後に迫る群賊や猛獣(死の恐怖)から逃れるため、ひたすら西へ走ってきた旅人。
しかし、彼の目の前に突如として(忽然として)、絶望的な光景が現れます。
「この人 死を怖れてただちに走りて西に向かふに、忽然(こつぜん)としてこの大河を見て、すなはちみづから念言(ねんごん)す」
そこにあったのは、燃え盛る火の河と、逆巻く水の河。
旅人は足を止め、自分自身に問いかけます(念言す)。
旅人の「モノローグ(心の声)」
旅人は冷静に状況を見ようとしますが、見れば見るほど絶望的です。
- 「この河は南北に辺畔(へんぱん)を見ず」(この火と水の河は、南を見ても北を見ても果てしなく続き、岸辺が見えない=煩悩には際限がない)
- 「中間に一の白道を見るも、きはめてこれ狭小なり」(二つの河の真ん中に、一本の白い道が見えるが、それは極めて狭く細い)
- 「二の岸あひ去ること近しといへども、なにによりてか行くべき」(向こう岸までは近いように見えるが、炎と波に挟まれたこの道を、どうやって渡ればいいのか?)
- 「今日さだめて死すること疑はず」(ああ、私は今日、間違いなくここで死ぬのだろう)
「問い」こそが「求道心」の始まり
旅人はここで、「助かった!」ではなく「死ぬに違いない」と絶望します。
しかし、この「立ち止まって自分に問う」という行為こそが重要です。
ただ漫然と生きている時、私たちは自分の限界や死について深く考えません。
しかし、本当の危機に直面した時、「私の命はどうなるのか?」「このわずかな希望(白道)をどう歩めばいいのか?」と真剣に自問自答します。
この「生きる意義を必死に尋ねる心」こそが、仏教でいう「求道心(ぐどうしん)」です。
「今日さだめて死すること疑はず」という絶望的な自覚は、諦めではなく、真実の救いを求めるための、痛切なスタートラインなのです。
迷いは続く
「進むこともできず、留まることもできない」
極限状態の旅人は、ふと後ろを振り返り、「戻ろうか……」と考え始めます。
「まさしく到(かえ)り回らん……」
果たして、引き返す道はあるのでしょうか?
旅人の葛藤は、次回さらに深まっていきます。
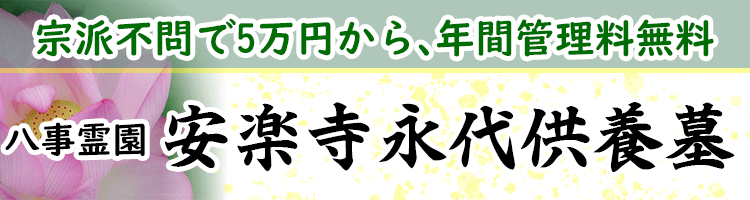



コメント